 坂本 大河 さん
坂本 大河 さん
私は入学の時から札幌南高校の中でも特に忙しいと言われている野球部に入ることを決めていたため、どんなに忙しくても部活後は東進で勉強することを習慣化し、たとえ短い時間であっても学習を欠かさないよう意識していました。東大レベルの対策では、苦手を得意にすることは簡単ではないため、まずは普通を得意にすることが大切だと思います。自分は英語に絶対の自信を持っていたため、高校1~2年生の間には受験レベルまで完成させ、その上で数学や理科の対策に時間を掛けられるようにしました。東大受験においては、共通テストはもちろんですが、何よりも2次試験へ向けた記述対策の取り組みが重要です。私は東進の過去問演習講座や志望校別単元ジャンル演習講座をやり込むことで対策をしましたが、演習を効果的に行うためには基礎力や定石力の徹底が不可欠です。東進の講座を通じたインプットで本質をつかみ、未知の問題にも対応出来る地力を付けた上で、出来るだけ演習の時間を多く取り、アウトプットの訓練を積み重ねてください。学習内容やスケジュール管理など、生徒に合わせた学習が出来る東進の個別最適化のシステムは自分にピッタリで、東進以外の選択肢は考えられない程おススメです。最後まで諦めず、志望校合格に向けて頑張ってください!
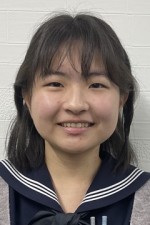 余湖 理彩子 さん
余湖 理彩子 さん
私は中学校3年間練成会に通い、高校受験終了後すぐ東進衛星予備校に入塾しました。高校入学前に英単語1800と英熟語750を修得し、数学も二次関数まで予習したので、高校の授業についていくのは容易でした。平日の学校帰りには毎日東進に行き、勉強しない日をつくらないようにしていました。東進では数学の先取りと二次試験に対応できる学力の育成、高校では基礎力の強化と復習に努めるというように学習を棲み分け、取捨選択していました。どの科目もまんべんなくやって苦手科目をつくらないようにするのは地方の公立高校生の東大合格には大切だと思います。まんべんなく出来ると模試の総合点で下振れすることが減ってメンタル安定につながります。模試は本番に強くなるためにもたくさん受けて損はありません。地方にいながらも苑田先生や長岡先生の質とレベルの高い授業が受けられたことで合格に大きく近づけました。一緒に閉校時間まで残って勉強した友達の存在、校舎長や担任助手、先生方、両親からの理解とサポートが力になりました。ありがとうございました。
 増田 陽介 さん
増田 陽介 さん
私は高卒1年目の春から友人の勧めで東進に通い始めました。東進では、主に青木先生、苑田先生から現役時代には学ぶことのできなかった数学と物理の本質の部分を学ぶことができ、物事をしっかりと学ぶことの面白さを知ることができました。また、東進での浪人生活は基本的に一人であるため、常に本番を意識しながら勉強に取り組むことができ、それに加えて定期的に職員の方との面談を行うことでモチベーションを高め、計画的に勉強を進めることができました。校舎には浪人仲間があまりおらず、常に孤独との戦いでしたが、この1年間、ほぼ毎日朝から東進に通い夜まで勉強をするというサイクルを途中で乱すことなくこなすことができたのは、両親や数少ない仲間達、そして東進の先生方の支えがあったからこそだと思います。この1年間を通して東進で経験したことは私の人生にとって非常に有益であったと確信しています。短い間でしたが、ありがとうございました。東大に行きます。
 齋 美玲 さん
齋 美玲 さん
私は高1の3月に東進に入りました。吹奏楽部に所属していたのでかなり忙しかったですが、1年生で英語の高速マスター基礎力養成講座を4つ完全修得しました。それは後々すごく自分のためになったので、英単語1800を早く完全修得するよう促してくれた校舎の先生にはすごく感謝しています。この完全修得で自信をつけて、英語を得意教科として認識するようになり、英語への意欲が増して成績も伸びました。高2はかなり忙しく東大志望としては勉強量が少なかったです。しかし、高3の5月からは今までの勉強量不足を取り返すためにかなり勉強しました。周りに東大志望が少なく焦るときもありましたが、校舎の友達や担任助手の皆さん、担任の先生と話すことで頑張る気持ちを保つことが出来ました。共通テスト、二次試験の直前期は、さすがに緊張していましたが、校舎に来れば頑張っている友達がいたので何とか乗り切れました。雲の上の存在のように感じられていた東京大学を目指せたこと、そして合格できたのはこの校舎のおかげです。後輩の皆さんも努力を惜しまず頑張ってほしいです。ありがとうございました。
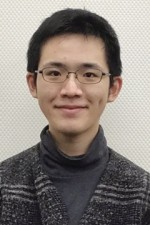 五十嵐 蓮太郎 さん
五十嵐 蓮太郎 さん
物理は、まず授業を受け特有の思考をトレースし、次にハイレベル物理(苑田尚之)により根本的な現象理解を得た。その理解を解説の豊富な問題集を解く・読むことで答案作成に使える形に変容させ、その過程で理解の誤りを修正し、精度を高めた。これにより現象のイメージと数式を往復する速度を上げた。その後の第一志望校対策演習講座は数多の未知の問題を提供してくれた。物理において大切なのは『理解から演習へ跳躍、遡行的に理解の欠如を埋める』反復作業だ。化学は理論・無機・有機、全ての分野で理論に基づく理解に努めた。経験則と現象・物質のイメージをリンクさせ、問題を通して定性的関係に慣れた。その為に京大本番レベル模試を数多く受け、未知の設定を既知のそれに変えていった。地道ではあったが徐々に処理速度は上がっていった。以上のように東進コンテンツを上手に活用した結果、合格へと至ったと思っている。理科の学びの奥深さを感じながら学習を進める為に、東進が不可欠だったと今振返って思う。
 竹内 友基 さん
竹内 友基 さん
結論から話すと僕が京都大学に合格できたのは東進の授業と模試のおかげだったと思います。僕は中学1年生の時から東進に通い始めたのですが、映像授業によって先取り学習をすることができ、同学年の人たちより明らかに有利になることができました。学校の授業では習ったことの復習になるので、どの内容もすっと頭に入ってきます。特に高校の理科では先取り学習で同級生たちより問題演習を多くこなし、合格に直結したと思います。実際の問題形式を忠実に再現している共通テスト本番レベル模試と京大本番レベル模試では、自分の実力を正確にはかることができ、自分に足りないもの、それを補う方法をいち早く知ることができます。同じ志望の人たちの中で自分はどの位置にいるのかということはもちろん、過去の先輩方と比べてどうであるかを詳しく知ることができ、目標を明らかにすることが容易になりました。皆さんも東進の授業と模試を最大限活用して夢をつかんでいってほしいと思います。心から応援しています。頑張ってください。
 鈴木 照正 さん
鈴木 照正 さん
私は高1の1月に東進に入り、最初は高等学校対応数学を受講することで先取り学習を実行できました。数学は高3からでは習得に限界があるため、早めに手をつけてある程度の得点を見込めるようにしておくと、受験期に理科の学習に時間をさけるので良いです。それ以降は苑田先生のハイレベル物理と高等学校対応化学を受講しました。物理は難関大攻略の上で重要だと思います。独学で物理を勉強しようとすると公式暗記になりがちなので、理解しながら物理を学習していくためにも物理の受講は重要です。数学的に物理を考えていく苑田先生の授業は入試で微積の考え方が問われる難関大で非常に役に立ちます。過去問演習講座の大学入学共通テスト対策と国公立二次・私大対策はできる限り早く一周目をするのが良いと思います。特に二次は別解も多いので、一度解いた問題を再び解くのは効果的です。志望校別単元ジャンル演習講座は難易度が高く、終わり切らないこともあるので優先順位をつけて取り組むと良いと思います。最も点数を伸ばすのは問題演習です。そのためにも予習を行い、少しでも多くの演習量を確保しましょう。
 岩下 幸生 さん
岩下 幸生 さん
私は東進の最も優れた点は質の高い教材が豊富にあることだと考えている。講座に関してもレベルや内容に応じて多数の講座が用意されており、過去問演習講座、志望校別単元ジャンル演習講座、高速マスター基礎力養成講座などの映像授業以外の学習教材も豊富である。これらの豊富な教材を、いかに自分にあった形で使えるかが成績の上下に直結するといえる。担任助手の先生は多くの人にとって最適に近い学習計画案(テンプレ)を持っている。その案は「間違いがない」学習計画ではあるが、人によって、学校によって勉強の進捗や環境、方法の合う、合わないには違いがある。東進は豊富な教材量があるからこそ、どの教材をどのように使うのかを担任助手の先生と話し合いながら自分なりに選択していくことが重要である。私の場合は、高校が受験勉強にあまり時間を割かない高校だったことや、国際物理オリンピックの勉強に時間が必要だったこともあり、他にあまり例がないパターンだった。担任助手の先生がその辺りも含めて理解してくれたおかげで、東進をうまく使って合格することができたと思う。
 栗村 咲里奈 さん
栗村 咲里奈 さん
私は高二の冬から東進に通い始めました。東進に入塾した理由は、部活が忙しくても自分のペースで受講ができることと家から近いことが魅力だったからです。東進で一番活用していたのは過去問演習講座です。共通テスト対策の過去問講座は過去問+東進作成の対策演習の計十二回あり、豊富かつ洗練された問題で十分に演習を重ねることができ、心強かったです。国公立二次・私大対策の過去問演習も素早い返却と丁寧なアドバイスで自分では気づかない弱点を見つけることが出来ました。また、偏差値から自分の位置を知ることができる科目もあり、自信にもつながりました。また、担任の先生との面談も大きな心の支えになりました。勉強のスケジュールの立て方や、学校の勉強との両立の不安なども先生と一対一で話すことによって解決策を見い出し、やる気を維持することが出来ました。私が大阪大学に合格できたのは、家族や友達、そして東進の先生方のサポートがあったからだと思います。本当にありがとうございました。
 髙木 結徠 さん
髙木 結徠 さん
「君は絶対受かるから先生を信じろ」。私は、三年生になって模試の度に涙を流しながら心が折れそうになった時東進の先生にそう言われました。私は高校三年間ずっと絶対に後悔したくないという一心でどんな時でもペンを握り続けました。模試で格別高い点数を取っていた訳でも、もともと天才的な頭脳を持っていた訳でもありません。それなのに東進の先生はずっと私のことを信じて、勉強についてアドバイスをしてくれました。 そして担任助手の先生は学習面はもちろん、生活面の悩みも聞いてくれていつでも心の支えになってくれました。 受験期は勉強すればするほど不安になって、学力落ちたなって思うと思います。でも、頑張って頑張って苦しんで悩んでそうやって合格した後の達成感は素晴らしいものです。東進の先生方が、応援してくれたから、自分のことを信じてくれていたから、私は努力し続けられました。時にはうまくいかないこともあるかもしれません。でも努力は必ず、実ると思います。東進の先生方は、そのことを実感させてくれました。
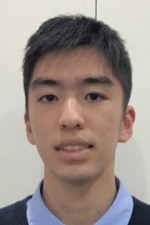 加藤 慶己 さん
加藤 慶己 さん
僕が志望校に合格できたのは東進の様々なコンテンツをフルに活用できたからだと思います。特に東進は授業がすばらしいと思います。映像授業であるため、苦手な所を繰り返し見たり、自分の都合に合わせて受講できるのは部活をやっていた自分にはとても適していました。そして、テキストはどれも要点がまとまっていてわかりやすく、模試の前にはいつも東進のテキストを見直すようにしていました。また、東進の本番レベル模試はとても役に立ちました。他の模試だと出題範囲が限られていることが多いですが東進は早いうちから本番を想定して模試を受験できました。そして、東進の模試は返却がとても速いので効果的に復習して力をのばすことができました。僕は、共通テストの直前期には今までの本番レベル模試で間違えた所を徹底的に復習し、本番で自己最高点を大きく更新しました。みなさんも志望校合格に向けて頑張ってください。応援しています。
 木村 恭司朗 さん
木村 恭司朗 さん
大学に合格するにあたり、特に取り組んで良かったと思うことが2つあります。1つ目は、「先取り学習」です。東進の映像授業を活用し、できるだけ早く先取りを済ませました。これにより、模試の数が多くなる夏より前に過去問等の演習ができました。演習からの知識の再確認という一連のサイクルを他の受験生よりも多くこなせます。実際、模試を受けると復習のみで一日が経ってしまうこともあります。夏前までの蓄積が、夏以降の学力のノビに役立ちます。2つ目は、「知識にどん欲になること」です。重要公式や教科書等で強調された部分は、多くの受験生が知っています。差をつけるためには、普段ざっとしか目を通していない箇所に根気を持って読むことです。事実、私は二次試験で、直前に確認した英熟語が出、おかげで問題が解けました。このように、受験生活は何かと根気のいるものですが東進を存分に活用すれば、着実に学力は向上します。ぜひ、第一志望合格に突き進んでください。
 齋藤みなみ さん
齋藤みなみ さん
私は高1の4月から東進に入りました。1年の時は模試の成績も全然よくありませんでしたが、良くも悪くも気にせず受講と高速マスターを頑張りました。東進の共通テスト本番レベル模試は難しいですが、毎回欠かさず受験したことでテストの傾向や緊張感に慣れることができました。私は週6で部活動がありました。部活後はなるべく東進で受講や自主勉をやりたかったので、毎朝7時半には学校に行って学校の授業の予習等をしました。3年間毎日朝勉をしたことは確実に自信につながりました。校舎ではどの時期に何をするといいのか明確に示され、面談が頻繁にあったので、沢山相談しながら学習計画を立てられました。また、自分の志望大学に通う担任助手の人たちに会えたので東進に毎日行くことが自分のモチベーションにもなりました。東進の過去問演習講座はとても充実しているので、10年分は早めに終わらせて2周目に入るととても良いと思います。ですが、何よりもできることをひたむきに継続してきたことが合格につながったのだろうと今は信じています。
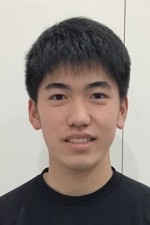 東海林 源真 さん
東海林 源真 さん
私は、高校一年生の後半から東進に通い始め、数学の先取りと英語の学習を行いました。入塾以前は、数学は学校の授業に追いつくのがやっとで、英語は嫌いな科目ではありましたが、東進での学習のおかげで、数学では校内順位で上位に入ることもできるようになり、英語は今井先生(サトイモ)のおかげで、英語に親しみを感じるようになり、音読にも力を入れたことでいつのまにか得点源になりました。そして、受験勉強を通し、私が大事だと思うこと3選を紹介します。其の一、間違った問題は「この問題が本番出たら解けるのか」と自分に問いかけ、解けるようになるまでその問題と対決すること。其の二、漢文と英語は音読すること。其の三、わからない問題を聞いたり、模試での点数を競ったりできるような仲間を持つこと。勉強は、やってOKではありません。解けることが目標です。勉強に対する姿勢から変えていきましょう。
 石沢 匠哉 さん
石沢 匠哉 さん
私は高校一年の頃から東進へと入り、その時から勉強に力を入れていました。そんな生活の中で私が最も大切だと感じたのは「目標を立てて勉強する」ということです。1年生の頃は東北大合格といった何年も先のことを目標としていたため、モチベーションも上がらず成績をうまく伸びませんでした。しかしながら2年生に上がってからはまず直近の模試に対して目標を立てて勉強していくことで勉強のモチベーションを維持し成績を上げることができました。この様にして2年生では大きな目標を1つ立てるということではなく、小さな目標を立て続けて勉強していくことで成績上げ2年生での共通テスト同日体験受験では数学で合格点付近を取ることができました。これを読んでくれている皆さんもこれからの生活では大学合格という長期的目標だけではなく、模試に標準を合わせた短期的目標、そして同日体験受験では1教科だけでも合格点を取るといった中期的な目標を立てて、モチベーションを保って勉強をがんばってください。
 大塚 隆平 さん
大塚 隆平 さん
私は高3の6月から入学しました。過去問演習講座の共通テスト対策を活用し、共通テストの過去問をたくさん解き、解説授業を何度も視聴して使い倒しました。夏からは学校が終わると毎日、東進の校舎に通い、開校時間はずっと勉強するつもりで生活しました。効率の良い勉強法を確立するには、自分に合った勉強法を見つける必要があり、必然的に勉強時間を取らなければなりません。また、効率と量がかけ合わさった最高出力の学習を目指すべきです。私は個人的な疲れやモチベーションを理由に勉強しないことを避けるため、とにかく校舎に毎日登校することを目指しました。受験勉強は辛いものです。特に試験直前期は生きた心地がしませんでした。自分の背中を押してくれたのは、これまでの自分の努力です。「ここまでやったから大丈夫」と思えるくらい勉強してください。1秒でも多く校舎で勉強し、周りに圧倒的な差をつけて勝利してください。最高の景色が待っています!
 飯沼 慶大 さん
飯沼 慶大 さん
自分は高2の夏休みくらいから、東進衛星予備校に通い始めました。数学は好きで得意だったけれど他の科目はとても苦手でした。その苦手科目の中でも自分が一番成長できたと感じたのは化学です。化学の講座を受講することによって高1のときに分からなかった内容が分かるようになり、化学を大きな武器にすることができました。また、高3では過去問演習講座の大学入学共通テスト対策を積極的に活用し、8月の共通テスト本番レベル模試から成績が上がるようになりました。この講座は問題演習量が多くてくじけそうになりましたが、諦めずにやり続けて、成果に結びついたのでとても嬉しかったです。過去問演習講座の国公立二次対策では、問題が難しくわからない箇所が多かったので、解説授業を一生懸命に見ました。解説授業はとてもわかりやすく、たくさん活用して成績を上げることができました。皆さんも志望校合格に向けて東進の先生を味方につけて最後まで諦めずに頑張ってください。
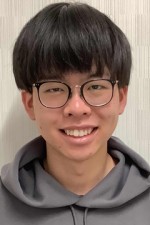 山田 快大 さん
山田 快大 さん
僕は公立高校入試直後から東進に通い始めました。高校1年生の時は数学と英語の映像授業と高速マスター基礎力養成講座で語彙力や計算力を養いました。高校2年生からは理科の基礎講座を始め、高校3年生で受験レベルの理科と数学の講座をとりました。高校1年生から単語などの基礎をしっかりとやっていたおかげで、英語は共通テスト・北大本試験の両方において大きな武器となりました。また、東進では模試が返却されるごとに面談があり、自分のできているところ、できていないところをはっきりとさせることができました。自分が苦手とする科目については、一つ一つ適切なアドバイスをしてくれ、それをこなしていくことで、テストを受けるごとに得点が上がり、共通テスト本番でも過去最高点を取ることができました。3年間、勉強が辛く得点が伸び悩むこともありましたが、先生方の励ましや支えもあり、最後まで目標に向かってやり切ることができました。自分の目標を実現するために、最大限東進を活用できると良いと思います。
 坂本 一太 さん
坂本 一太 さん
私は東進に通って合格への助けになったと感じる点は大きく分けて二つあります。一つ目は東進の講座の分かりやすさと、ただの暗記ではなく、事柄の理解をしっかり促してくれる点です。学校で習っただけではうまく理解できず自分のものにできなかったことも、東進の授業を受けるとしっかり自分のものにできました。また、映像授業であるため何回でも授業を聞きなおせるのも理解の一助となったと思います。二つ目は模試が充実している点です。本番の試験より難しく感じますが、その経験によって本番の試験が難しく感じることはほぼなかったです。また、模試の返却がとても早いのですぐに自分のできなかったところを復習することができます。さらに年間の模試の回数も多いのでたくさんの実践演習を積むことができます。そのうえ、模試受験者の母数も多いので志望校の判定は信用できるものだと思います。
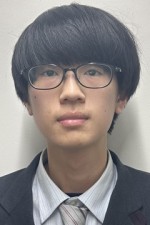 吉本 拓真 さん
吉本 拓真 さん
東進に入ってよかったと思う点は3つあります。1つ目は、勉強習慣がつくことです。自分はあまりに勉強時間が不足しており、入塾してたくさんの講座を取ることで毎日継続的な勉強をすることができるようになりました。 2つ目は、共通テスト本番レベル模試、大学別本番レベル模試がたくさん受けられることです。特に、東進の共通テスト本番レベル模試は難易度が高く、本番では焦らず解き切ることができた要因だと思います。 3つ目は過去問演習がたくさん行えることです。やはり過去問は解いておかなければなりません。数多くの問題を解き、添削してもらったことが非常に大きな財産になりました。 東進では志望校合格のために必要なものがたくさんあります。新札幌校の先生方は皆さん優しく雰囲気が良い出の、機会があれば行ってみてください。
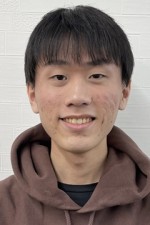 加藤 龍之介 さん
加藤 龍之介 さん
僕にとって東進の最大のメリットは自由に受講の計画を立てられることです。高校入学前に英語の高速マスター基礎力養成講座や数学の受講を進めておくことで、最初から勉強につまずかずに済みます。また、余裕があればどんどん受講できるので、先取り学習のツールとして最適です。勉強において重要なのは日々の復習と模試の解き直しです。大学受験では内容の深い理解と素早い情報処理能力が求められます。そのため、同じ問題に何度も取り組むことはとても効果的です。慣れるまでは面倒に感じることが多いですが、一度習慣となってしまえば成績は間違いなく上がっていきます。しかし、ただ同じ問題を解くのではなく、各問題の要点を確実に拾っていくことが大切です。また、自分の習熟度に合わせて勉強法を変えていく必要があります。何か悩みがあれば、学校の先生や担任助手の先生に質問するとよいと思います。最後に、東進は教材が豊富で模試の質もよいので、存分に利用して高校生活を充実したものにしてください。
 千葉 蛍太 さん
千葉 蛍太 さん
自分は過去問演習講座共通テスト対策が合格の一番の要因だったと思います。実際の過去問を解けることに加え、大問別の演習問題も数多く用意されていたので、非常に便利な学習ツールでした。自分は北大の過去問演習講座二次対策も取得しました。過去問演習講座の年度別演習は勉強量に応じて点数が上がっていくので、難しく点数が上がりにくい二次試験の勉強をするモチベーションにもなりました。 また、担任助手の先生との毎週の面談も効果的でした。過去問の演習履歴を確認して苦手分野をあぶりだし、解決のためのスケジュールを示してくれました。行き詰まりを感じた時にも勉強から逃げずに頑張り続けることができました。 自分は他の人に比べると入学が遅かったのですが、このような東進のシステムを利用して、入学時のE判定から合格に到達することができました。本当に東進に感謝しています。
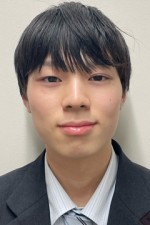 岩本 昴之 さん
岩本 昴之 さん
私は高2まで勉強習慣がついていませんでした。そのため春期から東進に通い始め、勉強習慣をつけるべくまずは校舎に行くようにしました。受験生になり、担任助手の方が自分の担当についてくださいました。スケジュール管理が苦手だった私には「この週は数学の複素数平面と化学の無機をやろうか」と一緒に考えてくれる面談が、非常に助かりました。 過去問演習講座共通テスト対策ではとにかく様々な形式の問題を解き、形式に惑わされず時間に追われないよう訓練できます。過去問演習講座二次試験対策では解答力を上げることだけでなく、問題の取捨選択ができるようになります。また、英作文や生物の記述問題など採点が分からない部分も添削が返ってくるので安心できました。
 間 翔太朗 さん
間 翔太朗 さん
共通テストが半年後に迫っていることに焦りを感じ、高3の7月に東進に入学しました。入学後すぐに過去問演習講座共通テスト対策の数学を解きました。結果として、半分ほどしか得点がとれず、ショックを受けました。自身の戦略では最低でも7割5分は得点をとりたいと考えていたので、半年で20点以上伸ばさなくてはいけないことがとても大変なことであるように感じました。しかし、東進の模試や過去問演習講座から間違えやすいパターンを理解するように努めた結果、徐々に得点が上がり、結果に繋がるようになってきました。東進の過去問演習講座共通テスト対策では、追試験の問題も演習できるので、たくさんの問題に触れることができました。共通テスト本番では十分なアドバンテージをつくることができましたので、2次試験も成功し、無事合格を掴み取ることができました。これから受験をする皆さん、しっかりと過去問演習講座を活用し、合格を勝ち取ってください。
 佐々木 悠陽 さん
佐々木 悠陽 さん
私は高校3年間を通して一番重要視していたのは計画です。やはり、強制力がないと行動できない人が多いと思います。高校入試で失敗した経験もあり、その際何が良くなかったかを考えた時、計画性の無さが敗因だと感じました。 大まかな勉強計画をカレンダーに記載し、次の日の計画は30分刻みで細かく計画を立てたのですが、その際に有効だったのが東進の授業です。家でも授業が見られるため、計画が立てやすく効率よく勉強できたと思います。受験期には北大の過去問演習講座で添削してもらい、東進生ではない友人にも差をつけられました。受験当日緊張はしましたが、積み重ねてきたことに自信をもって落ち着かせることができたと思います。皆さんが第1志望校に合格できることを祈っています。
 三和 愛奈 さん
三和 愛奈 さん
私は高校一年生から東進に入っていましたが、元々体力がない上に札幌の高校に通っていたこともあって、平日は全く塾に行くことができませんでした。それでも東進の先生たちは私のペースを理解してくださり、来校頻度が少なくても成績が上がるようにアドバイスしてくださいました。本当にありがとうございました。
東進の授業は時間的自由度が高く、私でも負担なく受講を進めることができました。平日に受講をしなくても週末や長期休みで予定のない日には必ず来校し、2コマずつ受講をすれば夏までには全部終わります。自分だけのルールを作り、それを確実に守っていくことが大切だと思います。私がおすすめしたいことは、社会(特に歴史)を早めに固めることです。私は3年生の夏から復習をはじめ、共通テストまでに仕上げることができませんでした。共通テストの結果が良くないと、二次試験の日まで毎日焦りと不安に襲われます。社会は定期的に復習することをおすすめしたいです。三年間お世話になりました。
 廣川 和志 さん
廣川 和志 さん
私は高校1年生から野球部に入部しました。引退するまでの間は勉強時間が取れず、1年の最初の模試で校内302位をたたき出しました。しかし、東進という学習空間が僕を校内27位まで成長させてくれました。なかでも過去問演習講座の大学入学共通テスト対策は、共通テストが苦手な僕から共通テストができる僕にしてくれました。難化したリーディングで満点でした。また、樹葉先生の難関化学はとても参考になりました。というのも、化学の本質的な部分にせまる授業は、「僕という人生は化学からできている」と思わせる程でした。僕は11月の河合共通テストプレまでずっとE判定でしたが、最後に自己ベストを出すことができました。それはチューターからの手紙のおかげです。最後までコツコツ勉強したものが勝利するのです。NO東進NO LIFE
 平澤 太一 さん
平澤 太一 さん
私は高1から東進に入りました。高1は塾の先生のアドバイスのもと、英語と数学を重点的に取り組みました。数学に関しては、先取りをたくさん行い、高校2年生の間には、もう学校で習う前から知っている状態になっていました。このおかげで、模試や定期テストなどでは高得点を取ることができました。次に英語に関しては、英単語は東進の英単語1800と単語帳を使い、高校2年生のうちには、受験に必要なある程度の単語はわかるようにしていました。理科と社会は、学校の授業をしっかり聞き、東進の講座を利用して、特に物理は本質的な理解を大事にしていました。私は社会の勉強を怠り、共通テストでもあまり良い結果を出すことができなかったので、早めに勉強した方が良いです。また、問題文を読み飛ばす癖や長い問題文を読まない傾向にあったため、それて点数を落としてしまうことがありました。特に化学などはちゃんと問題文を読むことが大事です。皆さんも受験頑張ってください。
 中田 結平 さん
中田 結平 さん
私は3年生になったタイミングで本腰を入れて受験勉強に取り組もうと思い東進に入りました。同じ志を持つ仲間とともに集中して勉強に取り組むことができる環境は自分にとってすごくモチベーションとなり、吹奏楽部がとてつもなく忙しかったような時期もかなりの頻度で東進を訪れることができました。それに加えてもう一つ私にとって大きかったのが過去問演習講座の存在でした。早いうちから問題に触れ、さらに授業できっちり復習してというサイクルができたのは、勉強の方針を決めるだけでなく自分の力を知ることができるという面でとてもありがたかったと思います。共通テストも二次試験も自分がとことん満足するまで演習できると、自信とともに本番への想定もできてかなり合格に近づくと思うのでまずはひたすら演習を回し続けることを推奨します。あと英単語はさっさとやってしまわないととても厳しい状況に陥るので、その辺りも意識してもらえると良いと思います。
 目黒 真義 さん
目黒 真義 さん
受験をするにあたり僕が心がけていたのは、圧倒的な勉強量です。僕はどんなに模試や定期テストで1位をとろうとも満たされないほど精神面が弱く、共通テストの前日も二次試験の前日も緊張で2時間半ほどしか眠れませんでした。しかし、問題用紙が配られ解答開始を待っている間、どの教科の前であっても不思議と受験に負ける気は全くしませんでした。これは、東進で頑張った勉強量の厚みからくるものだと思います。東進コンテンツでは特に今井宏先生の英語A組・上級者養成教室の受講が役立ちました。圧倒的速読力を手に入れ、共通テストも二次試験も英語を武器にして受験することができました。また、自分の弱点の精神面をカバーするため「自分が最強」であると思い込み「僕は最強だ」と口に出すことで、どんなに体調が悪くても、眠たくても負けない自信がつき、精神面を克服しました。受験を終え最も重要と感じたことは、どんなことも全力でやることです。学校では行事や昼休みを友達と全力で楽しみ、東進での勉強は根性で最後までやり通す。これが受験に勝利するポイントです!
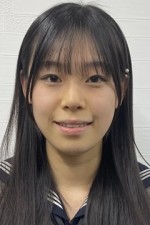 森 瑞葉 さん
森 瑞葉 さん
私が受験を通して大切だと感じた2つのことを紹介します。1つ目は受験日になるまで何があってもあきらめずに勉強し続けることです。私は北大志望だったのですが、3年生の4月の時点ではどの模試もE判定で、担任の先生にもこのままでは合格は無理と言われるほどでした。そこからはテストや模試の結果に一喜一憂せず、毎日苦手な科目から逃げずにバランスよく勉強していきました。その後は北大本番レベル模試で辛い結果のときもありましたが、無事合格することができたので、とにかく自分ならいけると信じて勉強をすることが大事だと感じました。2つ目は、どんなに勉強ができなくても1科目だけでも得意科目を作っておくことと、英単語や古文単語を怠らないことです。これさえ3年生までにやっておけば受験期がかなり楽になると思います。この2つのことをやって、あとは体調をしっかり管理すれば大丈夫です。
 山中 進之介 さん
山中 進之介 さん
偏差値が高くない中堅校から北海道大学に合格することができました。私が北大に合格できた理由は三つあると思います。一つ目は自分自身の為になる勉強をしたことです。東進の映像授業や高速マスターに加えて自分が買った参考書など、学校の勉強より自分の勉強、すなわち自分が志望校に合格するための勉強を優先しました。二つ目は自分なりの勉強のルールを作ったことです。例えば、英語を二時間やったら少し休む時間を作り、その後に数学などの違う科目をやるなど、自分のやる気が続くようにルールを作っていました。三つ目は東進の担任の先生との面談です。やる気が無くなった時や気分が落ち込んだ時に面談をすることでモチベーションが上がり、勉強に再度集中する良い機会になっていました。北海道大学を目指し始めたのは高二の終わり頃でしたが、自分がやるべきことを第一に考え実行すると同時に、東進の授業や面談も効果的に使って北海道大学法学部に合格することができました。
 中岡 擢 さん
中岡 擢 さん
理系は理科2科目の受験が必要です。そのうち1科目は得意でも、物理・生物・化学のなかでもう1科目は苦手だという人は、僕のように地学を選んでみてはいかがでしょう。教科書を読み込んでおけば北大の理系に入れます。あと一つ何か理系科目を得意にすればよいので、ハードルが下がることは間違いなしです。英単語は1年生のうちから毎日やりましょう。文法も1年生のうちにマスターできると後が楽です。長文問題を解くのは英単語と文法が終わってからにしましょう。リスニングの練習は3年生の初めからでも間に合いますが、英単語と文法ができていないと困ります。あと音読と日本語訳を、取り組んだ英文全てでやるのも大事です。数学は理系では青チャート、Focus Goldなどの参考書をやりましょう。その後は青木先生の「数学の真髄」を2年生のうちにやってください。これができれば数学はばっちりです。あと、東進には講座を受けなくても毎日来ましょう。家で勉強するよりも、東進にきてやったほうが進みます。
 和澤 怜央 さん
和澤 怜央 さん
東進に入って良かったです 僕は高校入学時から東進に通っていました。部活をやっていなかったので、一年生の頃から東進に通い続け、勉強を習慣化することができました。早い段階で受験勉強に取り組めたことが合格できた大きな要因だと思います。 これ以外に受験勉強をする上で大切だと感じたことは二つあります。 一つ目は模試をたくさん受けるということです。 普段勉強していて学力が上がっているのか不安になることが多々ありましたが、東進では共通テスト本番レベル模試や大学別本番レベル模試を何度も受けられるので成績を把握しつつ学習を進められたうえ、試験に慣れることもできました。二つ目は、過去問演習講座に早いうちから取り組むことです。共通テスト、二次のどちらも十年分以上揃っており解説授業まで付いているので先生の指示通り早くから進めましょう。辛くても勉強を続ければ成績に現れます。頑張ってください。
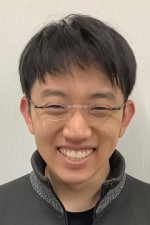 米沢 祐亮 さん
米沢 祐亮 さん
私が北海道大学医学部医学科に現役合格できた理由は、東進で自分の学びたいことを深められたことです。ただ受験を通過するためだけの勉強と、自分で学ぼうとする勉強では、学びの深さが違います。どれだけ深く勉強したかによって入試問題への対応力が決まっていきます。東進の映像授業や様々な過去問演習講座で本質を自由に学ぶことができたことが私の合格に繋がりました。私は、東進で苑田先生の物理の授業を取っていたのですが、一度で理解できない所は何度も受講し、自分のペースで受講と復習をできたので、演習や発展問題対策の時間も十分に確保できました。そこで付けた対応力によって、北大入試本番の難化傾向にも対処できました。東進のおかげで現役合格を掴めました。今までお世話になった人に感謝を伝えたいです。受験勉強はとても辛い作業です。心の支えとして私はコーヒーを毎日研究しました。皆さんも受験を乗り切るために日々の楽しみを探してみてください。
 対馬 匡洋 さん
対馬 匡洋 さん
受験はテニスと同じだと思います。テニスは焦り、熱くなりすぎるとミスが増え、体力切れになります。受験も同じことが言え、適度な緊張と余裕を持って勉強し、模試を受けることが大切です。テニスにおける本番を意識した練習、多種多様な相手との練習は、試合で勝つために重要です。受験も同じで時間を測って本番を意識した答案作り、1つの大学に絞らず複数の大学の過去問を解くことが大切です。自分は国公立二次の過去問演習講座で早期から東北大学の過去問を解き、その後、千葉大学や九州大学の過去問を解くことで、様々な出題傾向に対応できるようにしました。テニスは1人では出来ません。一緒にプレーする仲間がいて初めて成立します。この点に自分はとても恵まれていたと思います。同じ目標に向かって頑張る仲間、フレンドリーなチューターさんや職員さんに支えられ、最後まで諦めずに走れました。受験勉強はただ合格だけではなく、今後の人生に活きるたくさんのものを得られます。辛い・苦しいだけではなく、楽しんで乗り越えてくれればと思います。
 國井 翔太 さん
國井 翔太 さん
一年生のうちは、英語に本腰を入れて勉強していなかったので模試でも酷い成績を取ることも珍しくありませんでした。しかし、今井先生の講座を受けてから英文の読み方の基礎から応用までをしっかりと学ぶことが出来ました。また、英単語の高速マスター基礎力養成講座を何度も演習することで、さらに英文が読みやすくなり、模試でも安定した点数を取れるようになりました。共通テストの勉強をするにあたり、一番注意したことはどの科目もまんべんなく勉強するということです。どうしても苦手な教科や嫌いな教科を後回しにしてしまいます。かといって苦手な教科の勉強だけをやってしまうと、得意な教科で失点してしまうこともあります。特に、直前期に行う過去問演習はなるべく、1日で全教科を1年分解くことが大事だと思います。勉強ばかりだと息が詰まることもあると思うので、適度な休憩をはさみつつ勉強するべきだと思います。成績は思うように急に上がることはほとんどありません。毎日の積み重ねを大事にして勉強に励んでください。
 諸戸 和奏 さん
諸戸 和奏 さん
私は現役の頃、演習の大切さを知りませんでした。平日も休日も受講をし、参考書を眺め、知識をつけることこそが勉強だと思っていたのです。ですから、過去問演習講座共通テスト対策の年度別演習を行なった後にすることといえば、わからなかった分野のテキストの復習でした。しかし、点数は上がりませんでした。勉強をいくらしても共通テスト模試で600点を超えることすらありませんでした。がむしゃらに頑張って、頑張って、でも上がらない点数。少し病みました。そんな私にも転機が訪れます。担任助手の先生との出会いです。先生は私の頑張りを認め、私を適切な方向へと引っ張っていってくれました。その内容としては、大問別演習です。東進は年度別演習だけでなく、たくさんの大問別演習が教科ごとに大量に存在しています。問題を分野ごとに解くたび、何度も問われる内容や傾向を理解することができたのです。ですから私は、解けなくても分からなくても良いので、大問別演習に取り組み続けることを強くお勧めします。頑張ってください!!
 山北 樹 さん
山北 樹 さん
東進で学習する上で良かった点は、十分な問題の演習量を確保できるところだと思います。過去問演習講座では、約10回分の共通テストや国立二次試験及び私立大学の過去問を解くことができます。演習後には、詳細な解説を読んだり、東進の講師の先生方の映像授業を視聴したりして、自身の理解が不十分だった箇所を分析することができます。実際、私は世界史の試験で思うように点が取れないことが多々ありましたが、世界史の加藤和樹先生が教えてくださった解法を実践することで、内容の理解度が上がり、演習で目標点数を達成することができました。また、基礎的な学習を短期間で終わらせることができる点も東進の強みだと思います。高速マスターでは英単語や熟語などの基礎学習を短期で終わらせる仕組みが整っており、過去問を演習するうえで重要な土台を築くことができます。そして、校舎のスタッフの方々や共に勉強に励む仲間の存在は、受験勉強を送る上で心の支えとなりました。受験は苦しいこともありますが、皆さんが困難を乗り越えて合格することを願っています。
 桑田 蒼生 さん
桑田 蒼生 さん
何事も早めに行ったことが成果に繋がったと感じています。中3の3月から東進で先取り学習を進めたことで、高1、高2では常に上位層にいることができました。共通テストレベルの模試を高1から体験したことで、計画的に対策を行うことができました。高校で実施された共通テスト模試では学年1位をとることもできました。東進では高校3年間の勉強を高3・6月までに終わらせました。7月からは過去問演習講座共通テスト対策を用いて過去問演習に取り組みました。秋からは志望校別単元ジャンル演習、第一志望校対策演習に取り組みました。これらの講座ではAIが判定した苦手分野の克服と第一志望大学で出題されやすい二次試験の類題を解くことができました。高校生活ではサッカー部に所属し、友人と楽しい思い出がつくれました。毎日の部活が終わった後はとても疲れていると思いますが、気持ちの切り替えが大切です。僕は部活後に勉強をやるための空間を持つことで勉強習慣を作りました。皆さんも早めに受験対策を意識して、頑張ってください。
 四方 菜々美 さん
四方 菜々美 さん
私が東進で役に立ったと感じているのは高速マスター基礎力養成講座と過去問演習講座です。高速マスター基礎力養成講座は一年生の時からやっていて、特に英語の高速マスター基礎力養成講座に取り組んでいました。高速マスター英単語1800は合格するまで何か月もかかり苦労しましたが、中学時代と比べて覚える英単語が膨大になり、早期集中して一気に英単語を覚えることができたのですごく役立ちました。パソコンやスマホでクリックするだけで良いので、簡単に続けられて良いシステムだと思います。過去問演習講座は共通テストと二次対策に取り組んでいました。これは約10年分の問題と解説授業がついています。問題を解いた後にすぐ解説を見ることができるので、わからなかった部分がすぐに解釈でき、何度も確認できるので復習もしやすくとても良かったです。目標点に達すると色付きで表示されるので、ページをカラフルにしたいなと思いながら頑張っていました。みなさんも東進で高速マスター基礎力養成講座と過去問演習講座に取り組んでみてください。
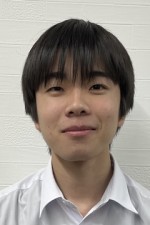 石原 悠稀 さん
石原 悠稀 さん
早めに今井先生などの英語長文を扱う講座をやっておくと、長文に対する嫌悪感が減った気がしました。また、高速マスター基礎力養成講座の英単語は、何も考えずにやってしまい、あまり頭に入らなかったため、通学の際に単語帳と併用して使用するのが良いと思いました。共通テストの国語は伸びるまでに時間がかかりましたが、直前に問題集をたくさん取り組むことで、本番まで順調に伸びていきました。東進の環境は、机と机の間に仕切りがあり、スマホをカウンターに預けていくことでかなり勉強に集中できました。東進の共通テスト模試の数学は、時間が全然足りないため、点数が低くても焦らなくて大丈夫です。数学、物理、化学は苦手分野を早めにやっておかないと、受験前はやるべきことが多くなり、結局後回しになってしまいます。ほぼ毎日最後まで残ってやっていても時間が足りなかったので、早めに受験勉強を始めましょう。
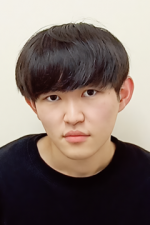 和澤 依央 さん
和澤 依央 さん
私は高校入学時から東進に通っていました。東進に通うことに決めたのは家から近く、中学・高校の友人が多く通っていたからという単純な理由でしたが、今ではあの時、東進に通うことに決めて本当に良かったと思っています。受講した講座には難しいものもありましたが解説がわかりやすかったのですごく力になりましたし、一年生の時から共通テスト模試で受験生と同じ問題を解いていたことで共通テストの点数は着実に伸びていきました。特に私は二次力がなくて学校の実力テストなどでもひどい成績だったので、合格することができたのは東進で共通テストに慣れていたというのが大きいと思います。また、私は三年の夏の模試で思うような点数が取れず、志望校を変えようと弱気になっていた時に校舎長の先生が面談で強い言葉をかけてくださったことでふっ切れて、第一志望に向かってまっすぐ勉強を続けることができました。
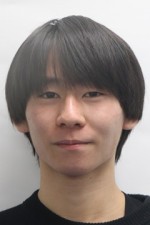 住吉 孝介 さん
住吉 孝介 さん
まず、高校に入って直後、東進の講座で数英の先取り学習を中心に、青チャートと並行して約半年間真面目に勉強に取り組みました。その後、東進にも行かずにまともに勉強もせず部活に明け暮れる日々が続きましたが、担任助手の先生に尻をたたかれ、なんとか東進に出向き頑張れました。3年生に入ってから受験モードに切り替え、共通テストと二次試験の過去問演習講座をやって対策を重ね、受験までの半年でかなり頑張って、点数も着実に伸びました。高校の最初で差をつけ、最後で逃げ切る形で成功して良かったです。
 今井 蓮 さん
今井 蓮 さん
私は高1の終わり頃から東進に通い始めました。最初は一人で勉強することに不安を覚えながら通っていました。そこで部活の友達を誘ってみんなで通いました。そうすることで東進に行くことが習慣になるのです。こうなれば最強です。みんなで高め合いましょう。次に具体的な話をします。1,2年生のうちは受験はとても難しくて高度なことをすると思っていると思いますが、そんなことはないと思います。なので1年生のうちから英単語をやることが一番大切だと思います。1,2年生のうちに1つの英単語帳を仕上げればもう合格は近いです。最後に諦めないことの大切さです。自分は模試でE判定を取ったことしかないのですが自分はやれると信じて第一志望を変えずに勉強し続けました。そうすると必ず合格はやってきます。頑張ってください!!
 山川 小侑介 さん
山川 小侑介 さん
中1の4月に練成会に入塾し、そこから高校部卒業まで計6年間練成会で勉強をし続けました。東進では高校入学後すぐに大学受験に関する情報を得ることができ、早いうちから受験を意識して高校生活を送ることができたのは非常によかったです。東進の受講をすることで先取り学習ができ、数学&英語で大きなアドバンテージを作れたのも大きな助けとなりました。毎週行われる担任助手との面談で学習スケジュールを立てながら、自学自習の習慣と進度を整えることで効率よく学習を進められたと思います。高校3年生になってからは共通テスト&北大二次試験の過去問演習講座をベースに繰り返し演習をすることで学力を高めることができました。北大二次試験の過去問演習講座にセットでついてくる解説授業が非常にわかりやすく、この解説授業で弱点の穴埋めを行うことができたのも合格の一因になったと思います。緊張せずに入試当日を迎えることが出来たのは、練成会で6年間勉強を頑張ったという自信があったからです。皆さんもコツコツ勉強を続けて志望校合格を掴みとって下さいね。
 韮澤 雄翔 さん
韮澤 雄翔 さん
私は、ラグビー部に所属していて、9月まで部活があり、平日に長い時間勉強することは難しい状況でした。ただ、少ない時間だとしても毎日勉強することが大事だと思ったので、部活後だとしても、できる限り毎日部の仲間と共に東進へ通うようにしていました。周りの受験生が早めに部活を引退し、勉強時間に差がつくと受かりづらいと考えたため、2年の春から東進に通い始め、早くから準備するようにしていました。また、科目別の対策については、数学と英語の基礎を早めに固めることが何よりも大切だと思います。理科や社会などは直前期からでも伸びるので、2年生が終わるぐらいまでは数学と英語の基礎を早めに固めることをおすすめします。また、難しい内容を早めに進めるよりは、各科目の基礎を満遍なく固めることが大事だと思います。
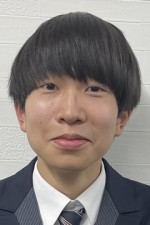 齋藤 颯心 さん
齋藤 颯心 さん
「努力は裏切らない」僕の3年を一言でまとめるならこれでしょうか。学力を上げる最も手取り早い方法は、学習時間の底上げに尽きます。僕の場合は家だとスマートフォン等の誘惑に負けてしまうので雨の日も風の日も雪の日もひたすら東進に通いつめました。周りの人から「東進に住んでる?」等聞かれだしたら合格です。偉い人は質×量というかもしれませんが個人的にはかなり圧倒的に量が受験勝利へのカギだと思います。他に意識していたことは模試、ひいては本番で実力を出し切れることです。事実、成績はかなり賢い人でも上下してしまいます。原因としては当日の肉体的、精神的コンディションに尽きます。これの対策はもう場慣れです。その点では東進の共通テスト本番レベル模試はどの塾よりも多い頻度で開催されるので1回1回大切に受けきることが大切です。東進の模試はかなり難しいので精神的に落ち着かない時もありますが、そんな時はどんどん担任助手の皆さんに相談しましょう。病んだ時も多々ありますが、くさらず、継続的な努力が合格には必要です。日々成長を意識して頑張りましょう!
 舛田 皓文 さん
舛田 皓文 さん
私が東進に通い始めたのは高3の夏からでした。ずっと英語が苦手だったので夏休み中は英語の映像授業を受け続けていました。学校帰りそのまま自分のペースで通えるので勉強する習慣を維持しやすく、また多くの人が通っているので私も頑張ろうとモチベーションも保ちやすかったです。 個人的に最もありがたかったシステムは共通テストの過去問演習講座で、問題用紙を印刷した後パソコンで時間を測りながら答えていきます。解答はパソコンに打ち込むことで自動で採点してくれるので、スピーディーな復習が可能です。特に国語や地理は場数がモノを言うのでぜひ過去問演習を活用しまくってください。最後にこの文章を見ている後輩へ、先に書いた通り私が本格的な受験勉強を開始したのは高3からですが、高2までに基礎力をつけることが大切です。高1,2のうちは勉強とのバランスを大切にしながら人生で一度しかない高校生活を楽しんでください。
 前田 直音 さん
前田 直音 さん
1、2年生の時は受験勉強と呼べるようなものをほとんどしておらず、3年生から本格的に勉強し始めたという感じでした。共通テストは4月ごろから少しずつ過去問を解き始めました。しかし、理科・社会はなかなか全範囲の復習が終わらず、全教科をそろえた対策は9月ごろに始めました。共通テストの対策には、東進の過去問演習講座や、共通テスト用の問題集や参考書、学校での講習を利用していました。次に二次試験は、9月ごろから少しずつ始めていましたが、本格的に始めたのは1月くらいからでした。二次試験対策では、赤本や東進の添削講座、学校の講習を利用しました。共通テストは、その出題形式に慣れること、二次試験(北大)では、標準的な問題を確実に取れる力や、公式や現象をただ覚えるのではなく、その根本を理解しておくことが大切だと思います。受験勉強をしていると、必ずだれでも伸び悩んだり逆に成績が急上昇する時期があります。周りの先生方はみんな「受験生は最後の一日まで伸びる」と言いますが、意外とこれは本当だったりします。苦しくても自分は最後まで伸びると信じて頑張ってください。
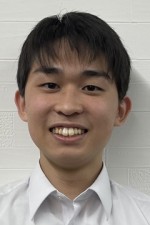 酢谷 侑生 さん
酢谷 侑生 さん
僕は大学受験で東進に助けられたことが3点あります。1点目は一緒に切磋琢磨できる友達と出会えたことです。面談が一緒だった友達と最後まで残って勉強したり、テストの点数で競い合ったりすることで成長できたと思います。2点目は時間の自由度が高いことです。部活を途中で抜けなくても授業を受けられたり、家でも受けられるところが魅力的だと思います。3点目は共通テスト模試です。二か月に一回のペースで模試を受けられるので、早めに共通テストの形式に慣れることができて良かったです。また、受験後に解説授業を見ることで自分の分からなかった部分や、解いたときに間違えた部分が分かるようになり、もっと効率の良い解き方を学ぶことができるのでレベルアップにつながったと思います。
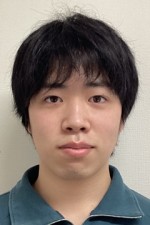 上野 遊佑 さん
上野 遊佑 さん
この度は、東進衛星予備校に通い、第一志望校に合格することができたことを嬉しく思います。合格発表一覧の中に自分の受験番号が無かった日から一年間、苦しいことも沢山ありましたが、私一人ではここまで勉強を進めることはできなかったでしょう。私は、東進が提供してくれる演習量の多さが学力向上に繋がったと思います。また、ただ演習を押し付けるだけでなく、担任の先生が定期的に面談をしていただき、ペースを決めてもらうこともできたため、自分で課題を設定し遂行することが苦手だった私は、安定して勉強を進めることができました。面談の際には、難しい問題にぶつかり落ち込んでいた時の不安を打ち明け、リセットしてまた打ち込むことができました。受験に向けて準備をする際、継続的に学習が出来るようなサイクルに持っていき、それを続けることが一番大変でしたが、逆にこのことを守ることができれば志望校合格の鍵になると思います。同じ受験に挑んだ身として、皆さんを応援しています。
 酒井 蓮 さん
酒井 蓮 さん
僕は高校1年生の4月に東進に入りました。入りたての授業で一番印象に残っているのは「高2の3月までに英語と数学を仕上げろ」と言われたことです。ですが、僕は英語がとても嫌いで、数学がとても好きだったので、高1や高2の頃は数学ばかりしていました。もちろん数学は仕上がり、英語は全くできないという状態になりました。高3になった時、僕は数学を仕上げたありがたみと英語をしなかった代償の両方を実感しました。みんなが数学に勉強時間を取られている中、僕は他教科に回せたので全体的に成績が良かったですが、英語のせいで受かるかどうか不安でした。高2までに英語も仕上げていたら、もっと高いレベルの大学を目指せていただろうなと思います。なので皆さんも高2の3月までに英語と数学を仕上げてください。他の教科は1年あれば確実に間に合うので心配せず仕上げてください。
 冨田 森慈 さん
冨田 森慈 さん
私は高2の時にバスケ部を辞めました。私は当初、中学の時と同様に交友関係を広めるために入部したのですが、先輩が引退しただけでなく、同級生が次々と退部し、部員が私を含め二人だけになってしまいました。ずっと部活は真剣にやっていたし、学校生活も楽しかったのですが、このままこの道を進んでも何も得られないのではないかという不安に襲われ、最終的にこれまで禁忌として目をそらしてきた退部という選択肢を選びました。そしてその代わりになりたい自分に近づくために京大合格という目標を設定し、全力で勉強に取組むと決めました。最初は周囲に反対されましたが、自分の決断を信じて勉強し続けた結果、成績がかなり伸びました。東進に入ったのは夏の京大本番レベル模試がきっかけです。非常に良質な問題だったので、ぜひ講座も受講したいと思いました。京大文系数学の講座は良質で考えさせられるような問題が厳選されており、また市販の問題集ではカバーできないマニアックかつ高度な内容も取り扱っていたので、自分の実力が伸びていることが実感できたし、数学の面白さも理解できました。何より使い古したテキストを会場にもっていったことは本番の安心感にもつながりました。東進に入ってよかったなと合格した今、実感しています。
 藤島 大聡 さん
藤島 大聡 さん
私が大学受験において活用したものは3つあります。1つ目は過去問演習講座共通テスト対策です。共通テストは基礎力が備わっているのは当然ですが、慣れが一番重要だと思います。過去問演習講座の1つの機能である大問別演習で各教科の苦手な大問を何度も演習し、過去問を時間配分を意識して解く、このサイクルによって共通テストの得点力はかなり上がったと思います。2つ目は過去問演習講座国公立二次・私大対策です。私は元々北海道大学志望で北海道大学の過去問演習講座を取っていました。札幌医科大学は北海道大学と傾向が似ているところがあり、特に北海道大学の数学を10年分やったことで札幌医科大学の数学の点数が大幅に上がったと思います。3つ目は東進模試です。特に共通テスト本番レベル模試は難易度が高く本番よりも少しレベルが高いです。そのためこの模試での間違えたことを分析し復習することで共通テストの点数を上げることができたと思います。
